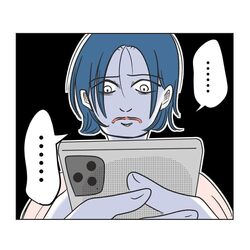知らないと損!? 育休中の社会保険料免除の条件は育休期間に注意!
育児休業(育休)中は原則として社会保険料が免除されますが、育休期間のとり方によっては、免除されなかったり、免除期間が1ヶ月分短くなってしまったりするのをご存じですか? 給与分と賞与(ボーナス)分の免除要件のちがい、2022年10月施行の改正「健康保険法」による免除要件の変更点についてもくわしく解説します。
育休中の社会保険料についての原則

毎月支払っている社会保険料が、育休中は免除になる制度があります。
社会保険料は、日ごろは給与から天引きされていて、あまり意識していないという方も多いかもしれません。でも、めやすとしては、月収15万円の方で毎月2万円ほど、月収20万円の方で毎月3万円近くも、社会保険料として徴収されているんですよ。これを支払わなくていいのは、ありがたいですよね。
免除になる社会保険料の金額については、記事の後半でもくわしく解説します。
育休中は原則として社会保険料免除
育休中は、通常、勤務先で給与から天引きされていることが多い社会保険料「健康保険」「介護保険料」「厚生年金保険」の徴収が免除されます[*1]。
育児・介護休業法で定められた育児休業期間(原則子が1歳まで、最長で2歳まで延長可)はもちろん、勤務先に独自の育児休暇(育児目的休暇制度)があり、子が3歳になるまで育児休暇をとれる場合は、育児休暇中も社会保険料免除の対象となります。
参考記事>育児休暇とは? 育児休業との違いと知っておきたい9つのこと
社会保険料の免除期間は月単位・育休開始月から終了の前月まで
育休中の社会保険料が免除されるのは、育児休業の開始日がある月から、終了日の翌日がある月の前月まで。
たとえば、1月15日から6月15日まで育休を取得した場合、1月から5月までが免除期間となります。
社会保険料は日割り計算ではなく、1ヶ月単位で免除される点に注意しましょう。
社会保険料は免除期間中も「納めている扱い」に
育休中に社会保険料が免除されている期間中は、保険料を納めた期間として扱われます。
免除を受けても、将来受けとることのできる年金額が減ることはないので、安心してくださいね。
もちろん、免除期間中も被保険者としての資格を失うわけではないため、これまでと同じように、医療機関で健康保険証を使うことができます。
育休中の社会保険料が免除されるための手続き
育休中の社会保険料の免除のための手続きは、事業主、つまり会社がおこないます。
したがって、育休をとる人が、社会保険料免除のために特別な手続きをする必要はありません。育休を取得すると、自動的に社会保険料も免除されることになります。
社会保険料は、会社(事業主)と社員(被保険者)が折半して支払っています。社会保険料免除の手続をすることで、会社にとっても保険料を支払わなくていいメリットがあるということですね。
会社がおこなう手続としては、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」という書類を、育休期間中に、管轄の年金事務所(事務センター)に提出する、というものです。
短期の育休は社会保険料免除の対象にならないことも
育休は性別を問わず取得できるものなので、育休期間中は男性も女性も同じように社会保険料の免除対象となります。
ただし、同じ月の中で始まって終わるような短い育休をとる場合、育休期間が月末日を含むか、14日間以上の育休を取得していないと、社会保険料の免除対象になりません(2022年10月~)。
男性は女性と比べて、短期間の育休を取得するケースが多いため、社会保険料の免除条件を知らずに育休期間を決めて、後から「損をしたかも?」と思う方も多いようです。育休期間を決める際に、気をつけておきたいポイントです。次の項目でさらにくわしく解説します。
育休期間と社会保険料が免除になる条件

育休中に社会保険料の免除対象となるための条件をくわしく見てみましょう。
2022年10月1日以後に開始する育休については、健康保険法の改正によって、社会保険料免除の条件が見直されています[*2]。この改正は、とくに男性に多い短期の育休取得に大きく影響するものです。
毎月の給与の社会保険料が免除になる条件
毎月の給与にかかる社会保険料の免除条件は、次のとおりです。
■育休期間が月末日を含む
■同一月中に育休が開始して終了する場合、14日以上育休を取得する(2022年10月~)
上のどちらかの条件をクリアしていないと、育休中の社会保険料は免除されません。
2022年10月からの改正前は、月末日を含まない短期の育休は一律で社会保険料の免除対象から外されていましたが、改正により、14日以上であれば免除対象に含まれるようになりました。
毎月の給与の社会保険料免除要件は、改正により緩和され、対象が拡大しています。
賞与(ボーナス)の社会保険料が免除になる条件
賞与(ボーナス)の支給される月に育休をとる場合、金額が大きい賞与の社会保険料が免除になるかどうかは気になりますね。賞与にかかる社会保険料の免除条件は、次のとおりです。
<2022年9月30日まで>育休期間が賞与月の末日を含む場合
<2022年10月1日から>育休期間が賞与月の末日を含み、1ヶ月を超えている場合
2022年10月の改正前は、ボーナス月の末日を含んでいればどんなに短い育休であっても社会保険料の免除対象となっていましたが、改正により、1ヶ月より長期の育休だけが免除対象になりました。
賞与(ボーナス)の社会保険料免除要件は、改正により厳しくなり、対象が縮小されています。
社会保険料免除を最大にする育休期間のポイント
育休中の社会保険料の免除をなるべく多く受けるための育休期間の考え方としては
・月末日から育休を開始する
・月末日までで育休を終了する
・期間内に月末日を含まない場合は、14日間以上とる
ということがいえます。
現実としては、育休期間は思うようには設定できないことも多いです。育休開始日は産休終了の翌日にほとんど自動的に決まったという女性は多いでしょうし、育休の終了日は、保育園にいつから入れるか、慣らし保育がいつまでかかるかとの兼ね合いで決めざるを得ないことも多いでしょう。
ある程度自由に日程を決められる場合には、社会保険料の免除要件も、育休期間を考える材料にしてみてくださいね。
月をまたぐ育休は終了日を月末にしないと損をする?
【例】
・10月1日~翌年9月30日(月末日)まで育休を取得 → 10月~翌9月までの12ヶ月分の社会保険料が免除
・10月1日~翌年9月29日(月末日ではない)まで育休を取得 → 10月~翌8月まで11ヶ月分の社会保険料が免除、9月分は免除にならない
月をまたぐ育休では、育休終了日が月末かそうでないかで、育休最終月が社会保険料免除になるかどうかが決まります。
社会保険料の免除の対象となるのは、育休の開始日がある月から、終了日の翌日がある月の前月まで。つまり、育休を月末日までとれば、育休期間終了日を含む月が、社会保険料免除の対象となります。
逆に、月をまたいだ育休を月の途中で終了してしまうと、育休の最終月は社会保険料免除にならないというのが原則です。
短期の育休は終了日を月末にするか14日以上とらないと損をする?
【例】※2022年10月以降のケース
・10月1日~10月14日まで14日間の育休を取得 → 10月分の社会保険料が免除
・10月1日~10月13日まで13日間の育休を取得 → 10月分の社会保険料は免除されない
前述したとおり、その月の給与にかかる社会保険料の免除対象となるには「育休期間が月末日を含む」もしくは「育休が同一月中に開始して終了する場合、14日以上育休を取得する(2022年10月~)」のどちらかを満たしていなければなりません。
そのため、育休期間中に月末日を含まない場合、取得日数は14日以上にしておかないと、社会保険料が免除になりません(2022年10月1日~)。
とくに男性が育休をとる場合、短期間のみ育休を取得するケースが多いため、気をつけましょう。
2022年10月の育休中の社会保険料免除要件改正のポイント
2022年10月の育休中の社会保険料免除要件改正のポイントは、同一月内で始まって終わるような短期の育休をとる場合、育休日数に関わらず、月末を含むか含まないかで社会保険料が免除になるかどうかが決まってしまうという不公平な状況が改善したことです。
具体例を見てみましょう。
| 改正前 (2022年9月30日までに開始した育休) |
改正後 (2022年10月1日以降に開始した育休) |
|
|---|---|---|
| 1月25日~1月31日まで7日間の育休を取得 | 月末日を含むため、1月の社会保険料が免除 | 月末日を含むため、1月の社会保険料が免除 |
| 1月5日~1月11日まで7日間の育休を取得 | 月末日を含まないため、1月の社会保険料は免除されない | 月末日を含まず、14日以下なので、1月の社会保険料は免除されない |
| 1月5日~1月18日まで14日間の育休を取得 | 月末日を含まないため、1月の社会保険料は免除されない | 月末日を含まないが、14日以上なので、1月の社会保険料が免除 |
| 7月が賞与月で、7月31日のみ1日間の育休を取得 | 月末日を含むため、7月給与と賞与の社会保険料が免除 | 月末日を含むため、7月給与の社会保険料が免除、1ヶ月未満なので賞与の社会保険料は免除されない |
| 7月が賞与月で、7月31日~8月31日まで1ヶ月超の育休を取得 | 月末日を含むため、7月と8月給与の社会保険料が免除、賞与の社会保険料も免除 | 月末日を含むため、7月と8月給与の社会保険料が免除、育休期間が1ヶ月超なので、賞与の社会保険料も免除 |
【ケーススタディ】この育休、社会保険料免除になる? ならない?

実際に育休を取得しようとすると、まだまだ「こういうケースは社会保険料免除になる? ならない?」という疑問が出てくることも多いでしょう。育休期間・日数と社会保険料免除に関する疑問について、さらにくわしく解説します。
ボーナス月の月末に1日だけ育休をとるとおトクって本当?
いいえ。2022年10月の改正で是正され、ボーナス月の月末に1日だけ育休をとっても、ボーナスにかかる社会保険料は免除されなくなりました。
2022年9月までは、育休期間が月末日を含む場合、給与と同じように賞与(ボーナス)分も社会保険料が免除されていました。
しかし、社会保険料免除を目的に月末に1日だけ育休を取得するケースがボーナス月に偏り、不公正で制度の趣旨に添わないという問題がかねてから指摘されていました。このこともあって、2022年10月1日以降に開始する育休からは免除要件が変更されています。
2022年10月1日以降に開始する育休における賞与(ボーナス)分の社会保険料免除要件は次のとおりです。
育休をボーナス月の末日を含む1ヶ月を超えて取得した場合のみ、ボーナスの社会保険料を免除
たとえば、2022年10月1日以降のボーナス月に育休を取った場合、社会保険料の免除対象期間は次のとおりとなります。
【例】 ※12月がボーナス月の場合
・12月31日(月末日)に1日だけ育休を取得 → 12月の給与の社会保険料は免除、ボーナスの社会保険料は免除にならない
・12月31日(月末日)から翌年1月31日(月末日)まで1ヶ月超の育休を取得 → 12月の給与とボーナス、翌年1月の給与の社会保険料が免除に
月をまたぐ育休を2回に分割してとれば、月末を含まない育休終了月も社会保険料免除にできる?
できません。分割した育休を連続してとる場合は、ひとかたまりの育休という扱いになります[*3](問17)。
月をまたいで育休を取得した場合、月末を含まない育休終了月は社会保険料免除になりません。
ただし、1回めと2回めの育休の間で一度仕事に復帰する場合は、1回め・2回めの育休それぞれについて社会保険料免除の条件をあてはめるため、それぞれの育休が月末日を含むか、同一月内に開始・終了していて期間が14日以上あれば、社会保険料免除になります。
月をまたいだ育休となり、育休終了日が月の半ばになる場合は、たとえ月内に14日以上の育休があっても育休最終月は社会保険料の対象となりません。
育休の分割取得と社会保険料免除の条件について
2022年10月から、育児・介護休業法の改正により、育休を分割してとることが可能になります。
ただし、育休を2回に分割してとる場合でも、育休期間が連続していると、社会保険料免除のための育休期間を計算する際には「ひとかたまりの育休」という扱いになり、月末日を含まない育休終了月は社会保険料免除対象にはなりません。(※例2)
分割した育休取得期間に間隔があいている場合は、それぞれの育休が月末日を含まなくても、同一月内に開始・終了して期間が14日以上あれば、社会保険料の免除対象となります(※例3)
【例】※2022年10月以降
1)10月1日~10月14日まで14日間の育休を取得
→同一月内に14日間以上育休を取得しているため、10月分の社会保険料は免除
2)10月31日(月末日)~11月1日までの2日間と、11月2日~11月15日までの14日間の育休を連続して取得
→10月31日から11月15日までのひとつの育休とみなされ、育休終了月の前月となる10月分の社会保険料のみ免除になり、11月分は免除にならない
3)10月31日(月末日)~11月1日までの2日間と、1日あけて、11月3日~11月16日までの14日間の育休を取得
→10月分は月末日を含むため、11月分は同一月内に開始・終了していて期間が14日間以上となるため、ともに社会保険料免除
同じ月内で育休を分割して2回とり、合計すれば14日以上になる場合、社会保険料免除になる?
はい、同一月中に育休を分割して2回とる場合、育休取得日数が合計して14日以上になれば社会保険料は免除となります[*3](問12)。
【例】
・10月1日~10月7日まで7日間と、10月14日から10月21日までの7日間、合計14日の育休を取得 → 10月分の社会保険料免除(同一月内に、14日以上育休を取得しているため)
産後パパ育休も社会保険料免除になる?
はい。通常の育休だけでなく、産後パパ育休中も社会保険料の免除対象となります[*3](問3)。
2022年10月から、産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が始まります。これは、男性の育休取得を促進するための制度で、これまでもあった育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間、取得することができる制度です。
産後パパ育休を同一月内で14日間とるが、うち1日は仕事をする場合、社会保険料免除になる?
いいえ、産後パパ育休期間中に月末を含まない場合は、免除になりません。社会保険料免除の条件になっている14日間という育休期間からは、就業する日は差し引かれます。
原則として、育休中の就業は認められていませんが、産後パパ育休は、勤務先と労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
ただし、就業した日数は、社会保険料免除の条件に関わる育休期間の日数からは差し引かれる点に注意が必要です。同一月内に産後パパ育休の開始日・終了日がある場合、就業日を差し引いた育休期間が14日以上ないと、社会保険料免除の対象になりません。
同一月内に産後パパ育休を14日間取得したとしても、そのうち1日は就業する場合、育休日数から就業日数は差し引かれるため、産後パパ育休期間が月末日を含まない限り、社会保険料は免除されません。
同一月内で土日を含む14日間の育休をとる場合、社会保険料免除になる?
はい、なります。社会保険料免除の条件に関する育休日数からは、土日や有給休暇など、本来は就業予定のなかった日を差し引くことはしません[*3](問10)。
育休期間に月末日を含まない場合、同一月中に14日以上育休を取得していなければ社会保険料の免除対象とはなりませんが、14日間には土日を含んでよいということになっています。2週間の育休をとれば、月末を含まなくても、社会保険料免除になるということですね。
ボーナスの社会保険料免除の条件になる「1ヶ月超」の計算方法(数え方)を知りたい。1ヶ月とは30日? 31日?
少し難しいのですが、30日とか31日とかいった日数ではなく、民法によって定められた「暦による期間の計算方法」を使って数えます[*3](問14)。くわしく説明しますね。
賞与(ボーナス)分の社会保険料免除条件は、2022年10月1日から「育休をボーナス月の末日を含む1ヶ月を超えて取得している場合のみ免除」となりますが、ここでいう1ヶ月とは、日数ではなく、次のように、暦によって計算されます[*4]。
■<月の初日から起算する場合>最終月の末日が満了月となる
(例)1ヶ月間とは、
1月1日~1月31日
2月1日~2月28日(平年)
2月1日~2月29日(うるう年)
■<月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ数字の日)がある場合>最終月の応当日の前日が満了月となる
(例)1ヶ月間とは、
1月20日~2月19日
3月15日~4月14日
■<月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ数字の日)がない場合>最終月の末日が満了月となる
(例)1ヶ月間とは、
1月31日~2月28日(平年)
1月31日~2月29日(うるう年)
3月31日~4月30日
前月月末日の応当日がない6月がボーナス月の場合、育休取得期間別の免除対象は、次のとおりとなります。
【例】 ※6月がボーナス月の場合
・6月1日~6月30日(月末日)まで育休を取得
→6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月ちょうどなのでボーナスは社会保険料免除にならない
・6月1日~7月1日まで育休を取得
→6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月超となり、ボーナスも社会保険料免除になる。7月は社会保険料免除にならない
・6月10日~7月9日まで育休を取得
→6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月ちょうどなので、ボーナスは社会保険料免除にならない
・6月10日~7月10日まで育休を取得
→6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月超となり、ボーナスも社会保険料免除になる
・5月31日~6月30日(月末日)まで育休を取得
→5月と6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月ちょうどなので、ボーナスは社会保険料免除にならない
・5月30日~6月30日(月末日)まで育休を取得
→5月と6月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月超となりボーナスも社会保険料免除になる
・5月29日~6月29日まで育休を取得
→5月の給与は社会保険料免除、育休期間は1ヶ月超となるが、6月の月末日を含まないので給与、ボーナスともに社会保険料免除にならない
免除になる社会保険料の金額

具体的に、社会保険料は育休中にいくらくらい免除されるのでしょうか?
社会保険料は、報酬月額によって決まり、また都道府県によっても若干異なります。さらに、40歳以上は介護保険料の負担が必要となりますので、年齢によっても変わってきます。
報酬月額とはボーナスも含めて、毎月受け取れる平均的な収入額のこと。報酬月額が20万円とは、ボーナスもあわせた年収が240万円ということです。
東京都の2022年(令和4年)3月分からの保険料額をもとに算出すると、次のとおりとなります[*5]。
なお、社会保険料は事業主と被保険者が折半していますが、下記は被保険者負担分のみ計算しています。給与の支給額などによって誤差が生じる場合もあります。
月収20万円・30代の場合、1ヶ月に免除される社会保険料は?
標準報酬月額:200,000円(報酬月額:195,000~210,000円)、40歳未満、東京都在住の場合
【健康保険】 月額保険料 被保険者負担分 9,810円
【厚生年金保険】 月額保険料 被保険者負担分 18,300円
▶1ヶ月の社会保険料として、免除額は28,110円となります。
月収30万円・40代の場合、1ヶ月に免除される社会保険料は?
標準報酬月額:300,000円(報酬月額:290,000 ~ 310,000円)、40歳以上、東京都在住の場合
【健康保険・介護保険】月額保険料 被保険者負担分 17,175円
【厚生年金保険】 月額保険料 被保険者負担分 27,450円
▶1ヶ月の社会保険料として、免除額は44,625円となります。
育休前後のお金に関する使える制度

社会保険料の免除にフォーカスして解説してきましたが、育休期間の前後には、社会保険料免除以外にも、さまざまな経済的支援が用意されています。お金が不安という方は、ぜひチェックしてみてください。
産休中も社会保険料は免除になる
育休中と同様に、産前休業・産後休業(産休)中も、社会保険料は免除されます。
以前は育休中のみ社会保険料が免除となっていましたが、2014年4月からは産休中も免除対象となりました。育休中と同様に産休中も、社会保険料が免除されている期間中も保険料を納めている扱いになります。健康保険証が使えなくなることも、将来受けとる年金額が減ることもないので、安心して制度を利用してくださいね。
育休中の住民税は徴収が猶予される場合がある
産休・育休中でも住民税は納めなくてはなりませんが、納税が困難であると地方団体の長が認める場合は、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます[
*6]。
ただし、住民税が免除されるというわけではありません。猶予というのは「待ってもらえる」という意味で、猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税しなければならないのが原則です。
住民税の徴収猶予を検討したい場合、まずはお住いの市区町村に相談してみましょう。妊娠したら母子健康手帳をもらいに行くのをはじめとして、妊娠・出産後はお住いの市区町村の役所の子育てを管轄する窓口とやりとりする機会が増えるはずです。お金に不安があると相談すれば、住民税の徴収猶予に限らず、使える制度を案内してもらえる可能性は高いです。
産休・育休中にもらえるお金がある
休・育休中には、一定の要件を満たせば、産休中には「出産育児一時金」と「出産手当金」を、育休中には「育児休業給付金(育休手当)」を受け取ることができます。
それぞれの概要や、対象期間、支給額は次のとおりです。
参考記事>手当金の手続きは忘れずに! 産休・育休中にもらえるお金まとめ
出産育児一時金
「出産育児一時金」とは、健康保険に加入している女性が出産する際の入院費・分娩費を補うため支給されるお金です。加入している国民健康保険や健康保険組合などから、子どもひとりあたりにつき、42万円支給されます。
(※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40万8,000円)
妊娠・出産は病気ではないので、自然分娩の場合、医療機関での支払いに保険がききません。そのため、分娩費用の支払額は高額になりますが、通常は、出産育児一時金でかなりの部分をまかなうことができるはずです。
出産手当金(産休手当)
「出産手当金」とは、出産のために仕事を休んだ女性に支給される手当金のこと。名前が似ているので混乱しがちですが、「出産育児一時金」とは別の制度。産休中は多くの人が無給になりますが、その場合の収入を補うことが目的です。
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(双子など多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、勤務を休んだことにより給与を得られなかった期間を対象として支給されます。
「出産手当金」の1日あたりの支給額の計算方法は、次のとおりです。
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額]÷30日×3分の2
育児休業給付金(育休手当)
「育児休業給付金(育休手当)」とは、育児休業中に給料をもらえないママ・パパに対し、雇用保険(国)から支払われる手当金。
育休期間に収入が途絶える(または、減る)ママ・パパは、原則、子どもが1歳になるまで(延長条件を満たせば最長で2歳になるまで延長可)の育休期間中に、手当金を受けとることができます。役割としては、「出産手当金」の育休版ということもできます。
「育児休業給付金」の支給額は、育休をとる直前6ヶ月間に受け取った給与を180日で割った“休業開始時賃金の日額”をもとに計算されます。
育休開始日からの期間ごとの計算式は、次のとおりです。
【休業開始6ヶ月以内】休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
【休業開始6ヶ月経過後】休業開始時賃金の日額×支給日数×50%
参考記事>育児休業給付金(育休手当)の支給金額は? 計算方法を徹底解説
育休後に給料が減った場合の社会保険料の特例
育休終了後に、育児などを理由に報酬が低下した場合には、被保険者が実際に受けとる報酬の額と、社会保険料の算出基準になる標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。そういった場合には、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするために、育児休業後に被保険者が事業主を経由して保険者に申し出れば、標準報酬月額を改定することが可能[*7]です。
育休後、時短勤務などで収入が少なくなる時期に、収入に応じて社会保険料も低く抑えてくれるわけですね。
改定する場合の標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後の3ヶ月間に受けた報酬(例:1月31日に育休を終了した場合、2~4月が対象)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。
育児により給料が減った場合の年金額の特例
3歳未満の子どもを養育している方で、育児などを理由に報酬が低下した場合には、将来受けとることになる年金額の計算に際して、子どもの養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を、当該養育期間(子どもが3歳に達するまでの期間。以下 同じ)の標準報酬月額とみなすことができます[*8]。
育休後に時短勤務などで収入が減ってしまっても、将来の年金額が減らないようにしてくれる制度です。
まとめ
育休中・産休中には原則社会保険料が免除となります。社会保険料が年々上がっていくなか、ほとんどの方にとって、社会保険料免除の金額は無視できるものではないはず。育休期間は自由に設定できない場合もありますが、ある程度、期間を決めることができる場合は、育休期間と社会保険料免除の要件もぜひ、検討材料に入れてみてくださいね。
あわせて、社会保険料免除以外の経済支援もフル活用して、お金の不安なく子育てにのぞみたいですね。
(執筆:エボル/構成:マイナビ子育て編集部)
[*1] 厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料 (健康保険・厚生年金保険)の免除」
[*2] 日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要」
[*3] 厚生労働省「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」
[*4] 民法第百四十三条「暦による期間の計算」
[*5] 協会けんぽ「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」
[*6] 厚生労働省「育児休業期間中の住民税の徴収猶予」
[*7] 厚生労働省「育児休業等終了後の社会保険料 (健康保険・厚生年金保険)の特例」(2ページめ)
[*8] 厚生労働省「3歳未満の子を養育する期間についての 年金額計算の特例(厚生年金保険)」(3ページめ)