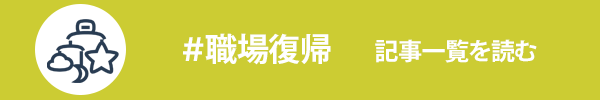知らないと損!働くママが会社で使える「5つの制度」って?
待ち望んでいた妊娠! でも働くママの中には、「赤ちゃんができたのは嬉しいけれど、仕事と子育て両立できるのかな」と不安に思う人もいますよね。また、子供ができると何かと出費も多くなるもの。育児休業中の収入についても気になるところです。今回は、働くママをサポートするさまざまな制度についてまとめました。
働くママのための制度(1)育児休業制度


働くママにとって強い味方となるのが「育児休業制度」。育児休暇や利用方法など、細かく解説します。
育児休業制度の内容
「育児休業制度」とは、「育児休業法」の法律に基づいて定められており、子供が1歳に達するまで休業することができるという制度。「育児休暇とどう違うの?」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、育児休暇とは、育児のために取る休暇などの一般名称のこと。育児・介護休業法に基づいた正式名称は「育児休業」です。
この制度は男女関係なく取得することができ、期間は、基本的には子供が1歳になる前日までです。女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得することができます。
ただし、保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所できない場合や、配偶者の死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子供の養育が困難になったなどの事情がある場合、1歳6ヶ月まで延長できます。
なお2017年3月、最長1年半だった育児休業の期間を2年まで延長する育児介護休業法が31日、国会で成立しました。2018年春までの実施を目指すとされており、妊娠のタイミングによっては育児休業の期間が延長できる可能性もあります。
育児休業制度の対象者
育児休業制度を利用するには、一定の条件が必要です。対象となるのは、以下のようなものとなります。
・同一事業主で1年以上働いている(日々雇用される者を除く)
・子供が1歳になっても雇用されることが見込まれる
・1週間に3日以上勤務している
・期間雇用の場合は、子供が1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること
この条件を満たしていれば、正社員でなくても、派遣社員や契約社員でも制度を利用できます。なお原則として、申請できるのは1子につき1回となっています。
育児休業制度取得の手続き
制度を利用するためには、以下のような書類を提出する必要があります。
・事業主への育児休業申請書類(会社によって異なる)
・育児休業等取得者申出書
・育児休業給付受給資格確認票
・被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書(第1回〜第6回)
・養育期間標準報酬月額特例申出書
・育児休業等取得者終了届
・養育期間標準報酬月額特例終了届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
多くの書類が必要で不安になる人も多いかもしれませんが、勤めている会社の担当部署や専属の社会保険労務士が対応してくれることが多いようです。育児介護休業法に基づき、育児休業の届け出を会社に行うときは、原則として育児休業取得日の1ヶ月前までに申し出を行う必要がありますが、予定日よりも早い出産となった場合や、病気などのやむを得ない事情がある時には、1週間前までに申し出ることができます。
育児休業給付金とは?
基本的に育児休業中は、会社には給料を支払う義務はありません。一定期間、収入がなくなってしまうのは厳しいものですよね。そんな時に頼りになるのが「育児休業給付金」です。休業中に会社から給料が支給されない・大幅に減らされたときには、雇用保険から育児休業給付金が支給日に支給されます。
対象となる人は「雇用保険に加入する65歳未満の人で、育児休業する前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」「休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと」「休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)」。雇用保険の加入が前提になっているため、自営業や専業主婦は支給の対象外となります。
また育児休業給付金の給付を受けるためには、育児休業の申請とは別に、「育児休業給付金支給申請書」で申請することが必要となります。忘れずに申請するようにしましょう。
働くママのための制度(2)短時間勤務制度


育児休業の期間が終了し、小さな子供のライフサイクルに合わせた働き方をするには、残業はもちろん、フルタイム勤務も厳しい場合も……。そんなママを支援するためにある制度が「短時間勤務制度」です。
短時間勤務制度の内容
短時間勤務制度は、対象者であれば1日原則6時間の短時間勤務をすることができるというもので、「改正育児・介護休業法」で定められています。会社は、原則1日6時間(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分〜6時間)の短時間勤務ができる制度を作り、就業規則に規定するなど制度化された状態にしなければなりません。この制度は、従業員(常時雇用労働者)数が101人以上の会社は2010年6月30日から、従業員数(常時雇用労働者)が100人以下の会社は2012年7月1日から義務化されています。
たとえば、この制度を利用すると、通常は9時〜18時までの8時間労働(休憩は1時間)であった場合、時短勤務は9時〜16時といった感じになります(休憩1時間、労働時間6時間)。なお、このように「改正育児・介護休業法」に定められたものとは別に、会社が独自で設けている制度もあります。短時間勤務を検討している場合、会社に問い合わせてみてもいいかもしれませんね。
短時間勤務制度の対象者
対象となるのは、「3歳未満の子を育てていること」。1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば、制度を利用できます。ただし、1日の労働時間が6時間に満たないパートの人には適用されません。
時間短縮された分の給料・年金は?
「改正育児・介護休業法」では、制度の利用で短縮された時間に対する賃金の保障までは求めていません。そのため、多くの会社は働いていない分の給与は払わないことが多いようです。
社会保険料(年金保険料)は、法に基づく時短勤務を利用した場合、給与が減る前の金額を基に保険料を払っているものと見なし、将来の年金受給額が減らない特例措置が設けられています。ただし会社独自の判断で設けた時短勤務では、給与が減った場合は年金保険料も下がり、将来の年金受給額が減少してしまいます。
働くママのための制度(3)時間外労働の免除


時間外労働、いわゆる残業も、小さな子供がいる場合、なかなか対応できないものです。できるだけ残業をセーブしたいというママのために設けられているのが「時間外労働の免除」です。
時間外労働の免除の内容
労働基準法では「残業」は、定められた労働時間の上限(1日8時間、1週40時間)を超えて働くこととされています。しかし、時間外労働の免除を会社に申請すると、残業を1ヶ月24時間、1年で150時間以内に抑えることができます。
時間外労働の免除の対象者
小学校入学直前の3月31日までの子供を育てる労働者が対象です。ただし、働き始めて1年未満の人や、1週間の労働日数が2日以下の人、日雇で働く人は対象外となります。この制度は男女問わず利用できます。
働くママのための制度(4)所定外労働の免除


「時間外労働の免除」では、残業時間を一定の時間にセーブすることができますが、子供の保育園のお迎え時間の都合などで、どうしても定時に退社しなければならないママもいることでしょう。そのようなママにおすすめなのが、「所定外労働の免除」です。
所定外労働の免除の内容
「所定外労働の免除」とは、残業を免除してもらうことができる制度のこと。就業規則等で決められた労働時間がたとえば8時間であれば、8時間を超えての勤務はすべて免除されます。
所定外労働の免除の対象者
対象となるのは、3歳の誕生日の前々日までの子供を育てる労働者です。主に対象外となるのは、働き始めて1年未満の人や、1週間の労働日数が2日以下の人、日雇で働く人。ただし、会社と従業員との間で決めたルール(労使協定)で、対象外と定められていることが必要となります。
働くママのための制度(5)深夜業(深夜勤務)の免除


接客などのサービス業は、勤務時間の一部が深夜(22時〜午前5時)に食い込んでしまうことも少なくありません。しかし、子育てと深夜の仕事との両立はかなり難しいものです。そのような時に利用したいのが、「深夜業の免除」です。
深夜業の免除の内容
対象者であるママが会社に申請すると、深夜業(22時から午前5時までの労働)を免除してもらうことができます。残業などで、しばしば退社が22時を過ぎてしまう……といった場合でも利用できます。
深夜業の免除の対象者
小学校入学直前の3月31日までの子供を育てる労働者が対象です。ただし、対象外となるのは「働き始めて1年未満の人」「1週間の労働日数が2日以下の人」「日雇で働く人」「働く時間のすべてが深夜業の人」「保育ができる同居家族がいる人」です。
家族の中で、ケガ・病気や出産前後の状態にない16歳以上の同居者がいる場合は、「自宅で保育ができる同居家族がいる」とみなされ、対象外となりますので要注意です。
まとめ
育児休業や育児休業給付金、短時間勤務制度、時間外労働の免除、深夜業の免除は、すべて働くママの子育てをサポートしてくれる制度です。職場復帰後、仕事とハードな育児の両立に悩むママは多いもの。復帰後にスムーズに利用できるよう、制度のことをあらかじめ勉強しておくのもおすすめですよ。