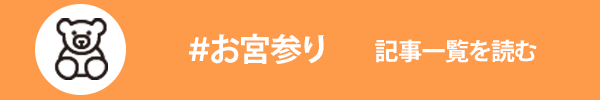お宮参り完全ガイド!マナー・行く時期・服装の準備・祈祷はどうする?
赤ちゃんが生まれると、これまでの生活にはなかったイベントが目白押し。産後1ヶ月の「床上げ」の後には、「お宮参り」がやってきます。赤ちゃんが生まれてから、初めて神社へのお参りをする日本の伝統行事にはどんな由来や意味が込められ、どのように行うとよいのでしょうか。見ていきましょう。
お宮参りとはどんな行事なの!?


赤ちゃんが生まれると、これまでの生活にはなかったイベントが目白押し。生まれた直後は「お七夜」に「命名式」。産後1ヶ月には「床上げ」もありました。そしてやってくるのが、「お宮参り」です。聞いたことはあるけれど、どういうものか正確には分からない、何をすればいいのかわからない、そんな方も多いのではないでしょうか?
お宮参りとは
お宮参りとは、赤ちゃんが生まれてから、初めて神社へのお参りをするという日本の伝統行事です。その土地の守り神に、赤ちゃんの健やかな健康をお願いします。
お宮参りをする理由
古くは、出産には血の忌みがあるとされており、それを祓う忌明けの儀式でした。また土地の氏神様の氏子として祝福を受ける儀式でもありました。現在では、神様に子供の誕生を報告して、健康と成長を願う儀式となっています。
どの神社にお参りすべき?
親としては、「○○大社や○○神宮など、大きい神社がいいのではないか」と思ってしまいがちですが、お宮参りは赤ちゃんが産まれた土地や、自宅から一番近い「産土(うぶすな)神社」にお参りするのが習わしでした。産土神社とは、「その土地を守っている神様」のことを指し、赤ちゃんにとって生涯一番身近な神様で、いわば赤ちゃんにとっての最高のパワースポットと言えるでしょう。
しかし、近年では「ご近所の神社で」というこだわりは薄れ、アクセスがよかったり、里帰り中の実家に近い他の神社などへのお参りも増えています。ご家庭によっては、「里帰り中に自分の地元で両親と一緒にお宮参りをして、里帰りから戻ってきたあとに夫の両親と2回目のお宮参りをした」と、2回お宮参りをする場合もあります。どこの神社で、何回する必要があるかは、夫婦や両家でよく話し合って決めましょう。
お宮参りのマナーとは


お宮参りは伝統行事。その土地によってマナーやしきたりが異なることもありますが、ここでは一般的なものをご紹介していきます。
お宮参りに行く時期とは
一般的には、男の子が生後31~32日目、女の子が32~33日目とされています。しかし地域によって違いがあります。京都などでは、早くお嫁に行けるようにと、女の子の時期の方が早くなっています。この点も時代とともに厳密ではなくなっており、おおよそ生後1ヶ月あたりに行うという風潮になっています。
一番は、子供や母親の健康状態などを考慮して、無理のない時期に行うこと。赤ちゃんの健康優先のため、基本的に一ヶ月検診を終えてからが望ましいです。そのため寒い地域では、冷え込む時期を避けて、温かくなってから行うケースも多く見られます。また猛暑の日中などは、正装をしているお母さん、赤ちゃん、ともに体調への影響が大きいもの。健康を崩さないよう、避けたほうが無難かもしれません。
お宮参りの日取りは決まっている?
日取りにおいても、特にこだわる必要はなく、「大安がよい」「仏滅が悪い」といったこともありません。逆を言えば、大きな神社の場合、結婚式が多い大安や、神社の特別な祭事がある日を選ぶと、参拝客が多く、赤ちゃんもお母さんも疲れてしまう可能性も。そうならないためにも、事前にお日柄や神社の予定を調べておくのもひとつの方法です。
誰が参加するの?
昔ながらのお宮参りは、赤ちゃん、父親、父方の祖父母のみでしたが、現代では母親も参加するのが一般的になりました。そのほかにも、
・祖父母が遠方に住んでいるため、両親のみで行う
・母方の祖父母も一緒に参加する
・両親の兄弟姉妹も一緒に参加する
といったケースもあり、昔ながらの風習を問わず「赤ちゃんの健やかな成長を家族でお祈りするイベント」として認識されています。
嫁ぎ先の地域によって習わしが違ってくることもあるので、両家の両親と話し合いながら決めていきましょう。
赤ちゃんと両親の服装についてのマナーは?
お宮参りでは、主役である赤ちゃんに「祝い着」を着せますが、実際は赤ちゃんに着せるわけではありません。赤ちゃんと抱っこしている人(祖母や母親)を包み込むように祝い着をかぶせ、抱っこしている人の背中で祝い着のひもを結んでいる状態です。
まずは、赤ちゃんの服装を「正式な祝い着の場合」と「略式の場合」の2つに分けてご紹介します。
赤ちゃんの服装(正式な祝い着の場合)


お宮参りでは、短肌着や長肌着などの上に、白羽二重という白絹で作られた内着を着せ、その上から祝い着を掛けるのが正式な装いです。
男の子の祝い着は、黒、グレー、紺、グリーンなどのカラーをベースに、松、鷹、鶴、龍、兜などの勇ましい柄の熨斗目模様(のしめもよう)が定番。女の子の祝い着は、ピンクや赤、黄色などのカラーに、桜や牡丹などの花、手鞠、鈴、花車、羽子板などの華やかな友禅縮緬が正式な祝い着となります。
仕上げに、男女とも、刺繍やレースなどが入ったスタイと、お宮参り用の帽子(大黒帽子)を付けます。スタイは祝い着が汚れるのを防ぎ、帽子は日差しや風などから赤ちゃんを守ってくれます。
また地域によっては、祝い着にデンデン太鼓、犬張子、お守り袋、扇子などの「縁起物」をつける場合もあります。
赤ちゃんの服装(略式の場合)


現代では、お宮参りにベビードレスを着せるというご家庭がほとんど。ベビードレスのみで行うケースや、ベビードレスの上から祝い着を掛けるケースもあります。ベビードレスは脱ぎ着が簡単で、オムツ替えや温度調節がしやすいのが魅力です。
ベビードレスを着せる場合は、短肌着や長肌着、コンビ肌着などの肌着の上にベビードレスやツーウェイオールを着せます。セットになっている帽子やスタイがあるなら、それを付けてあげてもいいでしょう。レンタルなどで祝い着を用意する場合は、そちらでセットになっているスタイと帽子を付けてあげましょう。
父親の服装
赤ちゃんが正式な祝い着を掛ける場合、格を合わせて一つ紋か三つ紋の紋付袴を、赤ちゃんがベビードレスを着る場合はブラックフォーマルの礼服やダーク系のスーツを着るのが主流になっています。しかし、近年では紋付袴を着る人は少なく、ほとんどの父親がスーツで参列しています。
スーツの場合、白シャツが基本で、ブラックフォーマルスーツには白ネクタイ、もしくはシルバー系のものを、ビジネススーツにはピンク系やブルー系の明るめの色を合わせましょう。靴はブラックの革靴で紐のあるものが一般的。神社ではお祓いなどの際に靴を脱ぐこともあるので、新品の黒い靴下がおすすめです。
母親の服装
和装、洋装ともに、赤ちゃんを引き立てるように、赤ちゃんの祝い着と色が被らないように注意しましょう。
■和装の場合
江戸褄模様の黒留袖が正装とされていましたが、現在では、無地の一つ紋や色留袖などの略式でもよいとされています。髪型は着物に合うようにアップにしましょう。
■洋装の場合
現代では、産後の体型・体調の問題や、授乳がしやすいことから、ワンピースなどの洋装を選択される方がほとんど。ワンピースを選ぶ際は、あまり華美になりすぎたり、肌の露出の多い服装になりすぎたりしないように注意が必要です。カラーは定番のブラックやホワイト、品のよいネイビー、明るいベージュ、華やかなピンクベージュなどをセレクトしておけば間違いありません。このあとの七五三や入園式などを見据えて、新しいものを購入しておくのもいいですね。
また、アクセサリーは赤ちゃんを抱っこすることも考えて、最小限にするのがポイントです。アクセサリーを付けるにしても、華美なデザインではなく、フォーマルなパール系のネックレスやイヤリングなどが無難。靴はフォーマルなブラックやネイビーのパンプスが定番です。ヒールが細くて高いと赤ちゃんを抱っこする際にぐらついてしまうので、太めのヒールで5cmくらいまでのものだと安定感があります。
祖父母が参列する場合も、ドレスコードを揃えて
祖父母が参列する場合も同様に、赤ちゃんや母親の服装をベースに、両家の格が合った服装にしましょう。両家が参加する場合、片方の祖母がワンピース、もう片方の祖母が留袖になってしまった、なんてことのないよう、事前に調整が必要です。特にお宮参りでは写真を撮ることも多いので、参加者全員のドレスコードを合わせることが重要です。
赤ちゃんの祝い着はどこで用意する?
赤ちゃんの祝い着は、購入するかレンタルで済ませるかの2通りが主ですが、最近ではレンタル衣装を利用する人がほとんどです。スタジオアリスやスタジオマリオなどの大手写真館なら、レンタルの祝い着を選んで写真を撮ったあと、そのまま神社に行ってお参りできるという便利な「お宮参り撮影プラン」があります。「祝い着はレンタルだけど写真は残しておきたい」と考えている人は、最寄りの写真館を探してみるのもいいかもしれません。
もし赤ちゃんの祝い着を購入する場合は、母方の実家から送られる習慣があります。値段としては5~10万円が相場といったところです。非常に高価ですが、男女ともに、七五三の祝い着として使うことができ、男の子はこれに袴などを揃えればOK。
七五三で着用する場合は、袖の直しや肩上げ、腰上げ、襦袢のつけ袖の取り外しなど、少々の手直しを加える必要がありますが、これは専門のお直し屋さんに頼むのとよいでしょう。普段はあまり馴染みがないお店かもしれませんが、百貨店、ショッピングモールなどに着物の仕立て屋や呉服店がテナントで入っていることが多く、一度相談に行ってみるのもいいでしょう。
赤ちゃんは、誰が抱っこするの?


参加者によっては、はじめに確認をしておかないと問題になりがちな、抱っこ問題。一般的には、赤ん坊を抱くのは「父方の祖母」とされていますが、これは産後の忌を避けるという意味から来ている風習であり、現代ではお宮参り自体が簡略化されているためにあまり気にすることはありません。
両家の了解が取れれば、両親や母方の祖母が抱っこしても問題はないので、参列を含めまずは両家の意見をヒアリングしてみましょう。
挨拶回りはしきたり?
古くからは、お宮参りが終わったら、千歳飴などを持って親戚やご近所などに挨拶回りをするしきたりがありました。しかし、現在ではこれも厳密ではなく、赤ちゃんとお母さんの体調などを優先して判断するようになっています。
もしも挨拶に行く際は、あらかじめ電話などで予定を伺っておくことが大切です。もしも先方から既に出産祝いをもらっている場合は、この挨拶回りでお返しを持って行くのもよいでしょう。
お宮参りで、事前に神社に確認しておくこと


お宮参りでは神社にお参りに行きます。その神社によって、祈祷ができる時間帯が異なっていたり、初穂料などにも違いがあったりします。結婚式が被っていると、祈祷ができないなんてこともあるので前もって調べておきましょう。
祈祷の予約
お宮参りの時にお祓いを受け祝詞を上げてもらう場合は、事前に社務所に問い合わせをしておくとよいでしょう。予約の要・不要は神社によって異なります。
初穂料(玉串料)の確認

お宮参りで祈祷してもらう際の料金のことを、初穂料、玉串料といいます。神社によっては料金が決められている場合がありますので、社務所に予約を入れる際に料金についても問い合わせをしましょう。
特に祈祷料金が設定されていない場合は、任意の額ということになりますが、5,000~10,000円が相場となっています。初穂料(玉串料)は、白赤の蝶結びの祝儀袋か、もしくは白い封筒に入れて渡します。表書きは、上段に初穂料(もしくは玉串料)、下段に赤ちゃんの姓名を書きます。
中袋がある場合は、表面に金額を書き、裏面には赤ちゃんの名前と住所を明記するのが一般的です。
撮影の可否や撮影場所について
神社によっては祈祷中の撮影はNGである場合もあるので、祈祷風景を撮りたい場合は事前に確認をしましょう。
お宮参りが終わったあとは?
外食をする
現在では、お宮参りのあとに、祖父母や親戚が集まって会食をするケースが多く見受けられます。赤ちゃんを連れての初めての大仕事を終えたあと、家に帰って料理を作るのはやはり大変なこと。外食すれば料理の準備や片付けをする必要がなく、久しぶりの外食は毎日赤ちゃんのお世話で忙しいお母さんの気分転換にもなるでしょう。
お店は前もって決めておき、事前に予約を入れておくと、当日の運びがスムーズです。移動を考慮すると、神社や自宅の周辺にあるお店がおすすめ。予約を入れる際は、お店に「お宮参りのお祝いで」と告げると、お祝い膳を出してくれたり、メニューを考慮してくれたりする場合もあります。そのほか、禁煙席をお願いする、赤ちゃんが泣いた場合のことを考えて授乳やオムツ換えができるスペースがあるかを確認する、個室や座敷(赤ちゃんを寝かせるため)があるかを確認しておくとよいでしょう。ネットで、乳児対応のレストランや和食店などを検索して選ぶとよいかもしれません。
また、ご家庭によっては「お食い初め」を一緒に行うケースも。お食い初めは、元来は「百日祝い」ともいい生後100日付近に行う儀式で、赤ちゃんが一生の間、食べるのに困らないようにと願います。お店を探す際に、「お食い初めプラン」があるかどうかで探してみるのもおすすめです。特にお宮参りに両家が揃う場合、一緒に済ませてしまうのも手ですよ。
ただし、両家が参加する場合に気をつけないといけないポイントがあります。それは「誰が支払いをするか」ということ。お宮参りのあとの食事会は、「自分たちで払う」「父方が持つ」「母方が持つ」といった特別な決まりがないため、当日を迎える前に両家の両親に相談しておく必要があります。
赤ちゃんもお母さんも両家の祖父母も、みんなが無理をせず楽しめる外食になればいいですね。
自宅で食べる
外食せずに、自宅や両家のどちらかで食事をするケースもあります。自宅の場合は、外食よりも周りに気を使わず、リラックスできるのがメリットですが、食事の用意をどうするか事前に決めておく必要があります。ピザなどの宅配でも構いませんが、せっかくのお祝いなので、豪華なお寿司や、お赤飯、尾頭付きのタイなどのお祝い膳を宅配してくれる仕出し屋さんに予約を入れておくのもいいですね。お食い初めを同時に行う場合は、外食のときと同じように仕出し屋さんにその旨を伝えておくといいでしょう。また、料理が届く時間を指定する場合は、ある程度余裕を持った時間帯に指定しておくことが当日慌てないポイントです。
宅配を使わない場合、お宮参りで疲れたお母さんの負担にならないよう、テイクアウトやお惣菜を買って済ませる方法もあります。もし手料理で義理の両親や自分の両親をおもてなししたい場合は、前日などから料理を用意しておくと、疲れて帰ってきたときに温めるたり仕上げたりするだけで済みますよ。
ただ、義理の両親をおもてなしするのに気疲れするお母さんも多いでしょう。また、主役である赤ちゃんの機嫌や体調も考慮する必要があります。お宮参り後はいったん解散し、気持ちと体力に余裕がある別の日に、お礼とお祝いの席を改めて儲ける方法もありますので、どのようなやり方が自分たちに合っているのか、夫婦で話し合ってみてくださいね。
お宮参り当日のスケジュール例
祝い着をレンタルしなかったり、神社で祈祷をしなかったりする場合は、赤ちゃんのご機嫌と参加者の都合に合わせてお宮参りを済ませれば問題ありませんが、お宮参りの衣装を写真館でレンタルする場合や、お宮参りのあとに会食をする場合は、念入りにスケジュールを立てておく必要があります。
ここでは、3つのスケジュール例をご紹介しますので、参考にしてみてください。
<お宮参りのスケジュール例1 祝い着レンタル、撮影あり、祈祷あり、両家で食事会あり>
期日までに、写真館で撮影と祝い着の予約、神社に祈祷の予約、料亭に予約を入れる。
↓
(当日)写真館へ行き、祝い着を着て撮影。
↓
お宮参りへ出発。手水舎で手と口を浄めて一揖(会釈)したあと、社務所に行き、
祈祷の予約をしてある旨を伝える。その際、持参した初穂料を納める。
↓
ほかの参加者などとともに待合室などで待ったあと、
職員の指示に従って全員で拝殿に移動。
↓
お祓い、祝詞奏上、巫女の舞などのほか、
神職や巫女さんの指示に従って玉串を捧げ、祈祷が終了。
↓
お守りや、お札、お食い初めなどのお椀といった「撤下品」を受け取り、
お宮参りが終了。「撤下品」の内容は初穂料によって異なるケースが多い。
↓
神社近辺の料亭に行き家族で会食
↓
帰宅
↓
(翌日)指定時間までに、写真館に祝い着を返却
<お宮参りのスケジュール例2 祈祷あり、家族で食事、別日に義理両親と撮影>
期日までに、写真館で撮影の予約、神社に祈祷の予約、料亭に予約を入れる。
↓
(当日)ベビードレスでお宮参りへ出発。
↓
お宮参りへ出発。手水舎で手と口を浄めて一揖(会釈)したあと、社務所に行き、
祈祷の予約をしてある旨を伝える。その際、持参した初穂料を納める。
↓
ほかの参加者などとともに待合室などで待ったあと、
職員の指示に従って全員で拝殿に移動。
↓
お祓い、祝詞奏上、巫女の舞などのほか、
神職や巫女さんの指示に従って玉串を捧げ、祈祷が終了。
↓
お守りや、お札、お食い初めなどのお椀といった「撤下品」を受け取り、
お宮参りが終了。「撤下品」の内容は初穂料によって異なるケースが多い。
↓
自宅近辺の和食店に行き家族で食事
↓
帰宅
↓
(別日)義理の両親を呼んで、写真館で撮影
<お宮参りのスケジュール例3 祈祷なし、食事会なし、祝い着レンタルで撮影あり>
期日までに、写真館で撮影と祝い着の予約
↓
(当日)ベビードレスでお宮参りへ出発。手水舎で手・口を清め、拝殿にお参り。
神主が駐在していない小さな神社なので、お参りのみで終了。
↓
写真館へ行き、レンタルの祝い着を掛けて撮影。
レンタル衣装はそのまま当日返却。
↓
帰宅
スケジュールは余裕を持って
お宮参りは、生後1ヶ月の赤ちゃんが主役。突然ぐずってしまったときや、授乳・オムツ替えのタイミングなどのことを考慮して、余裕のあるスケジュールを組んでおくことが重要です。両家の両親が参加する場合、集合時間に遅れるといったことがないように、時間に余裕を持って行動してもらうようにしましょう。
また、写真館で写真撮影をする場合は、赤ちゃんが寝ないように授乳直後の満腹なときを避けるケースがあります。赤ちゃんの毎日のサイクルを把握し、必要であれば写真館を予約する際に相談してみましょう。
まとめ
お宮参りは、赤ちゃんにとって生まれて初めての大行事です。また、お母さんにとっても、産後はじめての大きなお出かけとなるケースも多いでしょう。まずは体調を万全に整え、事前の準備をしっかりとして行いましょう。