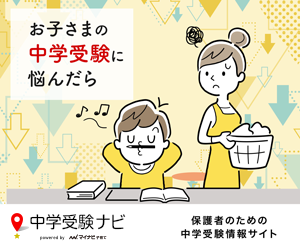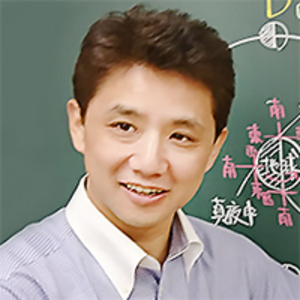整理整頓ができる子は勉強もできるの? 中学受験のためのモノの整理術
机の上や子ども部屋がいつも散らかっていると、一見、勉強もしづらそうですよね。しかし、部屋が雑然としているけれど成績優秀という子は珍しくありません。何がポイントなのか、整理整頓と学力の関係、そして、何かとモノが増えがちな中学受験のための整理術を紹介します。
キレイすぎる部屋、実は要注意!?

仕事ができる人は、机の上がいつも片付いていて、整理整頓が上手というイメージがあります。
同じように、勉強ができる子も整理整頓が上手というイメージを持つ方がいるかもしれません。
しかし、結論を先に申し上げると、部屋がきれいに片付いているからといって、成績も優秀だというわけではありません。
むしろ、モノが何も置いていない部屋は、教科書やテキストをどこかにしまい込んでいて、取り出すのに時間がかかってしまう、そういったデメリットもあります。
部屋の散らかり方と成績は比例も反比例もしない
もちろん、あまりにも部屋の中がぐちゃぐちゃで、足の踏み場がないような状態は好ましくありませんが、ある程度散らかっていても私はいいと思っています。
実際、成績優秀な子の部屋を見ると、キレイに片付いている子もいれば、一見雑然としているけれど、「前にこれに似た問題を解かなかったっけ?」と聞くと、「あ、これに似た問題はあのテキストの中にあった!」とパッと気づき、乱雑に積み上がった本の中からそのテキストをすぐに取り出してくることができるような子もいます。
後者タイプの子の場合、親御さんからすると、整理整頓ができていないように見えて、イライラするかもしれませんが、本人にとっては自分なりに整理ができているのです。
こういった場合は、あまり目くじらを立てず、口うるさく言わない方がいいでしょう。大事なのは、何がどこにあるか、把握しているかどうかです。
勉強に取り掛かるハードルを下げるために
何か集中しなければならないことに取り掛かる際は、できるだけアクション数を少なくできるように、モノの配置を整えておく方がいいでしょう。
効率よく勉強を始めるための「アクション数の法則」
たとえば、夕食前に塾の宿題をやるときに、部屋の中があまりにも散らかっていて、テキストが見つからない。そうなると、まず探すことから始めなければいけません。
かばんの中や、部屋の中を物色して、ようやくテキストを見つけ、机に座ってテキストのページを開く。そして筆記具を、かばんの中からゴソゴソする……。
こういった状況は勉強に取り掛かるまでのアクション数が多い状況です。
「勉強を始める」までに時間がかかってしまうと、面倒くささが増大して、やる気がそがれてしまいます。
そうならないためにアクション数を意識します。
たとえばですが、学校から帰ってきたら、友達と遊ぶ前に、塾のテキストにある宿題のページを開いた状態にして、筆記具もあらかじめ机の上に置きます。
そうすれば遊んで帰ってきた後、宿題に取りかかりやすくなります。
このように、やらなければいけないことがあるときのために、やり始めるハードルを下げるのです。
「アクション数の法則」の応用。ゲームはどこに収納する?
アクション数の考えは、子どもたちがつい誘惑に負けてしまいがちな、ゲームや漫画の収納にも応用できます。
こうした娯楽の品が目に入りやすく、取り出しやすい場所にあると、気になってしまい、勉強に集中できなくなります。
勉強に集中したい場合は、できるだけ手の届きにくい場所に置いておくとよいです。
たとえば、押入れの少し高い場所ゲームをしまって、椅子や台を使わないと取れない状態で保管しておくなどです。
こうするとアクション数が多くなります。「なんか、取り出すのが面倒なんだよな……」という場所に配置するのがポイントです。
中学受験のプリント類はどう整理する?
中学受験は小学生の受験です。
お子さんの成長度合い次第ですが、大なり小なり親のサポートが必要になります。
模試や塾のプリント類は親御さんが管理しているという家庭も多いでしょう。
「何かあったときのために……」と、通塾以来ずっと塾のプリント類をとっておく親御さんがいらっしゃいますが、どれだけ中身を把握できているのか疑問です。
把握できていないなら捨ててしまったほうがいい
たとえば、6年生のお子さんが算数の相似の問題が苦手だったとします。
そういうときに、「あ、この子は相似の基本がわかっていないのかも。じゃあ、5年生のプリントに戻った方がいいな」と、素早く5年生のプリント類を取り出せるのならよいです。
しかし、「あれ、相似か……、いつやったんだっけ? どこにあるんだ?」と把握できていないのであれば、思い切って捨ててしまった方がいいと思います。
たくさんプリント類があっても、それが整理できてない状態だと、勉強に取り掛かる速度を鈍らせかねないからです。
プリントが見つからないことでイライラしたり、集中力が下がるのも好ましくありません。
カテゴリーごとの収納とファイリングがおすすめ
整理整頓のポイントは、どこに何があるか把握できる状態にしておくことです。
おすすめはカテゴリーごとの収納とファイリングです。
まず、「学校」「塾」「習い事」など、お子さんの生活のフィールドごとに収納場所を分けておきます。
そして「塾」のものは、科目毎や学年毎にボックスを用意し、可能であれば単元ごとにファイリングしておきます。
収納のためのボックスやファイルは透明のものを選び、見やすい状態にしておきましょう。
お子さんが突然、上手に整理整頓できるようになることはありませんから、始めのうちは親御さんが手伝ったり、そのための道具を揃えてあげたりするとよいでしょう。
すべてを親がやってはダメ、子ども自身に把握させること
ただし、いつまでも整理整頓や片付けを親御さんが担ってしまってはいけません。
お子さんと一緒に、「これはここにしまっておくと、取り出しやすいし、探しやすいよね」などと親子で確認しながら、進めてください。
そうでないと、どこに何が置いてあるか、受験生本人がわからなくなってしまうからです。
はじめは親子で一緒に進め、慣れてきたら多少の細かいことは目をつぶって、お子さん自身に任せることです。
理想は低学年のうちから整理整頓が身につけられているといいのですが、中学受験に向け通塾が始まってからでも遅くはありません。
そうやって、何がどこにあるか把握できている状態にしておくと、勉強に取り掛かるスピードが変わってきます。
中学受験に大事なのは、見た目より「効率」
入試までの期限が決まっている中学受験は、いかに効率よく勉強を始められるかも重要なポイントです。
「整理整頓ができる子は勉強ができる」というわけではありませんが、モノを探す手間を省き、勉強を始めるハードルを下げることを意識しましょう。
※中学受験ナビの連載『今一度立ち止まって中学受験を考える』から記事を抜粋し、マイナビ子育て編集部が再編集のうえで掲載しています。元の記事はコチラ。